 |
10月7日第6日目、世界遺産カナディアンロッキーのツアーが始まる。
8:15 ホテルを出発したバスはバンフ国立公園を縦走するトランス・カナダ・ハイウェイを直走る。車窓には様々な地層帯が織りなす独特の山容が飛び込んでくる。まさしくここはカナダを象徴する大自然の真っ直中にいる。 |
 |
バンフ国立公園を貫いて走るハイウエイに朝日が差し込む。この辺りの紅葉は赤くならない樹木が多く、黄色みを帯びて最終期になるが、針葉樹とのコントラストが美しい。 |
 |
バンフを出発して数分でバーミリオン湖を通過する。朝もやの中にランドル山の輪郭が現れるが、ここは帰路の最後に立ち寄ることになる。 |
 |
カナディアンロッキーは樹林帯と岩塊の境界が特徴的な景観を形作っている。
↓バンフから約20分でカナディアンロッキーを代表するキャッスル山2728mが右手前方に見えてくる。この山からロッキー山脈のメインレンジとなり、大規模な海底隆起による造山運動が起きたらしい。 |
 |
 |
 |
ボウ川沿いに密生するロッジポールパイン(松)を両側に見ながらハイウェイを走る。この松は単独で生えることはなく、落雷などの山火事の後から一斉に生えてくるのが特徴。松傘は通常の温度では発芽せず、地中に埋もれた松傘が山火事の熱で眠りから覚めるようだ。名前の由来は、その名の通り小屋造りの建材に使われているところからきている。 |
|
|
 |
ハイウェイに架かるメガネのような橋が見えてきた。これは野生動物が道路を横断するために造られたもので、周囲の道路を柵で覆い主要箇所に動物保護のため設置しいる。 |
 |
9:10 出発してから約1時間でレイクルイーズに到着した。カナディアンロッキーの宝石と称される美しい氷河湖だ。正面の氷河に覆われた山がビクトリア山3459mで、氷河はビクトリア氷河、湖は英国のビクトリア女王の娘ルイーズの名が付いた。夏のシーズンが終わりボートハウスの赤底のボートが岸に上がっている。 |
 |
カナディアンロッキーでよく見かける野鳥。人間にもよく慣れていて近くまで寄ってくる。名前はクラークズ ナットクラッカー(後で図鑑で調べる)。クラークは探検家の名前でクルミ割りという意味がある。口ばしで松傘から器用に種を取り出すところからその名が付いた。 |
 |
晴天より半曇りの日の方が、湖の色がよりエメラルドに輝くとガイドが言っていた。氷河が削った岩粉が水の中に含まれていて、その量によって湖の色が変化する。 |
 |
 |
|
|
 |
シャトー・レイク・ルイーズは湖畔にあるカナディアンロッキーを代表するリゾートホテル。レイクルイーズを後に、次の観光スポットに向け出発する。道はトランス・カナダ・ハイウェイと分かれてアイスフィールド・パークウェイに入る。 |
 |
車窓にボウ・ピーク2868mが見えてきた。かなりの急斜面になっている屏風のような山だ。カナディアンロッキーの中でも古い地層帯が複数同時に見られる貴重な山だが、森林限界線がきれいに見える山でも知られている。 |
 |
 |
|
|
 |
10:05 クロウフット氷河が見える駐車場に到着。以前はカラスの足のように氷河が3本伸びていたが、一番下の氷河が崩れ落ちてしまい現在の形になったらしい。。 |
 |
 |
|
氷河が崩れ落ちるとき削り取った土砂が砂山のように見える。手前の水面はボウ湖の一部で、たまたまカラスが杭にとまっていた。 |
|
|
 |
ボウ湖とクローフット山(左)、ジミーシンプソン山(右)。その奥にボウ氷河があり、温暖化で後退したしたとき堆積した土砂が、氷河の溶け水を塞き止めボウ湖になった。 |
| |
 |
 |
|
ボウ峠でパークウェイを左折し駐車場に入る。徒歩で5分ほど下ったところにペイトー湖の展望台がある。 |
 |
 |
湖左手奥にペイトー氷河が見える。ペイトー氷河とボウ氷河は共にワプタ大氷原が源になっている。
|
ペイトー湖は季節により湖の色が変化する。氷河湖の特徴で氷河が多く解ける夏は乳白色に、少ない冬は群青色になる。浮遊する岩粉の量によって太陽光の反射が変化するからだ。10月頃はエメラルド色に輝く。正面の山がミスタイヤ山3094m、その右手にパターソン山、さらに右奥手がミスタイヤ谷で典型的なU字谷を形成している。
|
 |
ペイトー湖の観光を終え、さらにアイスフィールド・パークウェイの奥地へと走る。黄葉しているのはポプラの木で、この辺りではカエデは見当たらない。 |
 |
巨大U字谷を流れるミスタイヤ川に沿ってパークウェイを走る。左手にパターソン山3185m(ペイトー湖から見えていた)と急降下している鳥のように見える雷鳥氷河が見えてきた。温暖化の影響で胴と尾羽の一部が崩れ落ちているが翼を水平に広げて、頭が真下を向いている構図だ。 |
 |
ホルン型の山がケフレン山3307m、その手前の湖がウォーターファウル・レイク(水鳥湖)。山名の由来は、エジプト三大ピラミッドの一つ、ケフレン王の名を採ったもの。 |
 |
左奥に猫の耳のように二つ並んでいるのがカフマン・ピーク、右手がサーバック山3154m。山の中腹に岩盤の割れ目にくい込むように氷河がある。共にスイスの山岳ガイドの名前が付けられた連山である。 |
 |
 |
 |
正面に横筋状の地層が見える岩山がマーチソン山3337m。パークウェイはこの山の裾野を通り抜けている。 |
 |

氷河期時代以前はマーチソン山と繋がっていたウイルソン山3261m。この辺りに氷河が集まるクロッシングがあり連山を押し流していったらしい。この地点に休憩所があって小休憩する。
|

|
大きなヘアピンカーブを曲がりアイスフィールド・パークウェイは高度を上げる。左手山がシーラス山3215mで右手がサスカチワン山の裾野となりU字谷が狭まってきた。シーラス山の道路際に切り立つ断崖絶壁がウィーピング・ウォール(すすり泣きの壁)と呼ばれている。 |

アサバスカ山3491m
右奥にアンドロメダ山3450m
道はアサバスカ氷河観光の登山道 |
標高2030mのサンワプタ峠を越すとジャスパー国立公園に入る。やがて左手に山と山の谷間に氷河が見えてくる。

アイスフィールドセンター(眼下に小さく見える建物)から連絡バスに乗り中継所でスノーコーチ(雪上車)に乗り換えアサバスカ氷河散策に向かう。 |
 |

カナダ唯一の国産車で6輪駆動で氷河の坂道を走る。車体は1台1億円以上もして、タイヤは直径1.5m、幅1mで1本50万円もするそうだ。全部で23台造られて南極に1台あるだけで、全てここに集結しているそうだ。ここでしか乗れないスペシャルカーだ。 |
 |
スノーコーチの社内は様々な国の観光客でごった返す。案内の言語も行きと帰りではガイドが交代でしながら、それぞれの言語で説明する。 |
 |
氷河の急斜面も力強く登って行く頼もしいマシーンだ。奥にアサバスカ氷河が見えてきた。
|
 |
 |
|
終点の展望台で氷河散策を楽しむ。解けた氷河が流れ出ている水を飲むと10年長生きする?らしい。試に三回飲もうとしたら腹を壊すと言われた。二回20年で我慢する。アサバスカ氷河はコロンビア大氷原から押し出された氷河の一つで、他にドーム氷河などがある。 |
 |
 |
|
帰りの連絡バス車窓からアサバスカ氷河のモレーン(堆積土砂)と氷河の先端にサンワプタ湖が見えるが氷河から流入する土砂があまりにも多すぎて湖は大きくならずに小さくなっている。 |
 |
アイスフィールドセンターに展示されているキャタピラ式の初代スノーコーチ。夏の太陽熱で氷河が後退しつつある時に、キャタピラが更に氷河を削り取り、減少に追い打ちをかけると言われ、現在のゴムタイヤになったそうだ。 |
|
遅い昼食をアイスフィールドセンターのレストランで取り、来た道を折り返し帰路につく。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
15:40 ボウ湖に立ち寄る。ボウ谷を埋め尽くしたボウ氷河が地球の温暖化につれて徐々に後退を始めると、氷河が山々を削り自ら運んできた土砂を谷底に置いて行く形となり、氷河の解け水を塞き止めボウ湖が誕生した。 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
ボウ湖にある赤い屋根のナムタイジャ・ロッジ。ナムタイジャとはインディアンの言葉でテンという小動物の名前らしい。ロッジの後方に見える山は、レイクルイーズを発見した探検家トム・ウイルソンの料理人として働き、ロッジの建設者でもあるジミー・シンプソンの名がつけられている。 |
 |
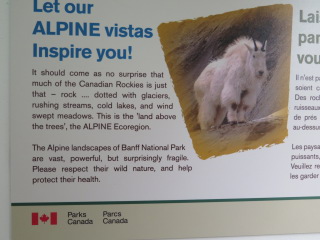 |
|
ハイウェイを走るトラックはカナダらしく超大型車が行き交う。背後に針葉樹林帯とキャッスル山。 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
17:00 最後に立ち寄ったバーミリオン湖とランドル山2949mの絶景ポイント。特にランドル山に陽が当たる夕方時は山が輝き最高の眺めになる。 |
|
|
|
17:20 宿泊ホテルに到着。夕食は市中にあるレストランまでショッピングしながら徒歩で行く。 |
 |

バンフのシンボルはカスケード山2998m。 |
 |
日系の土産物屋に入る。バンフは州税がかからないので(国税5%のみ)、ここで土産物を買うのが一番のお勧めだ。カナダブランドのRootsの店の看板が見える。35年前に来たバンフの街並みとは想像もつかないほどの賑わいを見せている。 |
 |
夕陽に映えるカスケード山とバンフのメインストリート。ショッピングを済ませてから夕食のレストランに向かう。今日のメニューは名物アルバータビーフ料理、ローストされたやわらかい赤身のビーフは、まさにカナダを代表する絶品の料理と言える。 |
 |
 |
|
 |